いきるためのメディア
2010-8-4
春秋社
田中浩也,渡邊淳司,藤木淳,丸谷和史,坂倉杏介,チェン,ドミニク
无
拡張現実、クラウド型コミュニケーション、情報を物質に変える3Dプリンタ。日常に浸透する情報技術によって私たちの生活はどう変化するのか。最前線の探究例から、“未来”を描き出す。
「メディア」という言葉には「媒介するもの」という意味がある。人と人との間で情報や気持ちを伝えるときに、その伝達を媒介するものがメディアとなる。古来、狼煙や紙も、発明されたときには時空間を越える最新のメディアであった。そして、近年、コンピュータやインターネットといったメディア技術の普及により、その伝達能力は飛躍的に向上した。コンピュータをメディアとして利用するとリアルタイムで地球の裏側の人と眼を合わせて話すことができ、自然環境では起こりえない人間と世界の相互作用を利用して情報を伝えることもできるが……。(br) 魔法的なメディアの持つ力とそれを取り巻く、人間の知覚システム、環境システム、社会システム(アーキテクチャ)を分析し、「改編」していくための現実的で、実践に結びつくコンセプトを提示。
渡邊淳司(ワタナベジュンジ)
1976年、東京生まれ。2000年、東京大学工学部計数工学科卒業。2005年、東京大学大学院情報理工学系研究科博士課程修了。博士(情報理工学)。2005~2009年(独)科学技術振興機構「デジタルメディア作品の制作を支援する基盤技術」領域さきがけ研究員。現在、日本学術振興会特別研究員、NTTコミュニケーション科学基礎研究所客員研究員。人間の感覚と環境との関係性を理論と応用の両面から研究している。近年は、学会活動だけでなく、文化庁メディア芸術祭等の芸術祭でも数多くの展示を行う
田中浩也(タナカヒロヤ)
1975年、北海道札幌生まれ。京都大学総合人間学部人間環境学研究科、東京大学工学系研究科修了。博士(工学)。東京大学助手、慶應大学講師などをへて、現在、慶應義塾大学SFC准教授。国際メディア研究財団非常勤研究員、マサチューセッツ工科大学客員研究員を兼任。デザインとエンジニアリングをつなぐさまざまなツール開発に取り組んでいる
藤木淳(フジキジュン)
1978年、福岡生まれ。九州芸術工科大学(現・九州大学)出身。博士(芸術工学)。日本学術振興会特別研究員。「実世界では有り得ないことが有り得る」表現の研究に従事。研究者として活動を行う傍ら、研究成果を作品として国内外の展示会やフェスティバルに発表している。受賞歴にPrix Ars Electronica 2008 Honorary Mentionsや第一〇回文化庁メディア芸術祭アート部門優秀賞等がある
丸谷和史(マルヤカズシ)
1975年、神戸生まれ。東京大学大学院人文化社会系研究科博士課程修了。博士(心理学)。日本学術振興会特別研究員、米国ヴァンダービルト大学研究員を経て、現在NTTコミュニケーション科学基礎研究所リサーチ・アソシエイト。専門は視覚の心理物理学。国際専門誌・国際学会にて多数の論文出版・研究発表を行う。近年では、視覚科学データベースVisiome構築・視覚科学実験のためのプログラミングツールPsychlopsの開発をはじめとした、研究のインフラストラクチャ改善のプロジェクトにも協力している
坂倉杏介(サカクラキョウスケ)
1972年生まれ。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修士課程修了。慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所特別研究講師、三田の家LLP代表。芸術とコミュニティの生成における「場」の働きを感性論的アプローチから研究している。また「横浜トリエンナーレ2005」など美術展への出展、大学周辺地域のコミュニティ形成や新しい「学びの場」を創出する「芝の家」「三田の家」の運営など具体的な「場」づくりのプロジェクトを展開
チェン,ドミニク
クリエイティブ・コモンズ・ジャパン理事。日本学術振興会特別研究員(東京大学)、NTT(ICC)研究員を経て、株式会社ディヴィデュアルを共同設立(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
第1章 ソーシャル・ファブリケーションの近未来/第2章 「確かな違和感」の生成アルゴリズム/第3章 浸透する人間科学のアーキテクチャ/第4章 自分を知るためのインタフェース/第5章 人と環境のあいだに生じるイマジネーション/第6章 コミュニケーションとしての統治と時間軸の設計
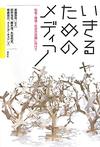
无